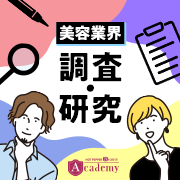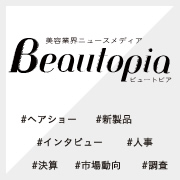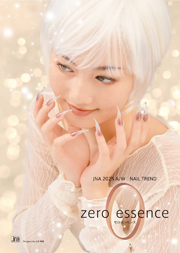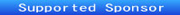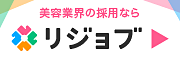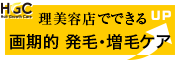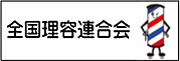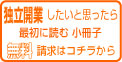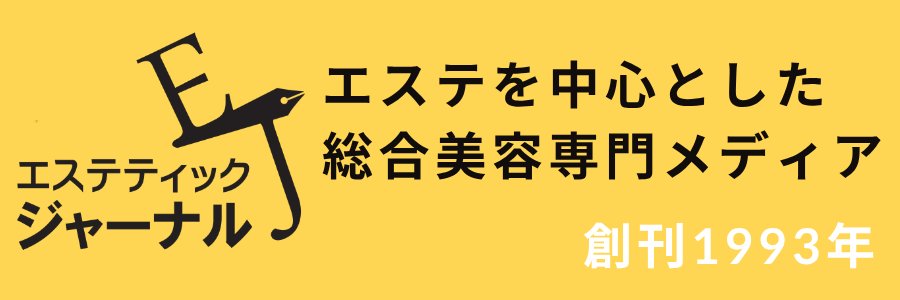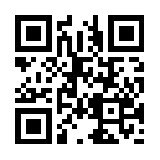理美容同時授業の要件緩和、実務実習時間の拡大、リモート授業の導入も
Posted on | 2月 28, 2025 | No Comments
第4回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会「理容師・美容師専門委員会」が方向性
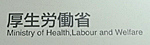 理容・美容の同時授業の要件緩和、リモート(遠隔)授業の実施などが近く実現しそうだ。
理容・美容の同時授業の要件緩和、リモート(遠隔)授業の実施などが近く実現しそうだ。
厚生労働省は2025年2月28日、第4回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会「理容師・美容師専門委員会」を開き、これまでの議論をふまえ論点整理を行うとともに、論点に対する検討の方向性(事務局案)を示した。年度内に開かれる次回委員会で、成案をまとめる予定。
事務局(生活衛生課)がまとめた論点は、
①必修課目と選択課目の履修内容について
②養成施設における実習のあり方、養成段階と就職後の人材育成の連携・接続について
③同時授業の特例(平成22年創設)の取扱いについて
④遠隔授業の実施について
⑤通信課程における面接授業の特例の取扱いについて(平成29年改正関連)
こられの論点に対し、事務局が示した方向性は
①「運営管理」(必修課目)で行われている接客等に関する教育に加えて、
・早期から自身のキャリアデザインを促すためのキャリア指導や就職活動や就業に必要な接客マナーに関する教育を実施する課目を新たに例示。
・「社会福祉」(一般教養課目群)において、知識の向上を図るため、様々な客層に対応できる人材を養成する観点から、高齢者や障害者の接客対応、外出が困難な高齢者等に対する出張理容・出張美容などに係る教育内容の充実。
②養成施設の判断において、地域の理容所・美容所との連携の下、実践的能力等の習得に向け、より効果的な教育を実施するための工夫として、現行の上限時間を超えて実務実習を行うことを可能とすることについて、どのように考えるか、として、
・必修課目(実務実習)については、現行120時間を180時間、270時間に拡大する案
・選択課目(専門教育課目)については、校外実習を現行48時間から72時間に拡大する案
③将来にわたって地域に理容・美容業に必要な人材を輩出できるよう、急速な少子化の進行や教員確保難への早急な対応として、
・同時授業の要件の更なる緩和を検討してはどうか。
④近年の情報通信技術の発展等を踏まえ、対面授業に相当する教育効果を維持しつつ、養成施設や生徒が多様な履修方法を選択することができるよう、理容師及び美容師養成課程の性格等を勘案の上、
・遠隔授業の取扱いや運用を明確化することとしてはどうか。
リモート授業に関しては、専修学校設置基準で定められており、理容師養成施設、美容師養成施設もこれに準じたリモート授業の導入を検討する方向が示された。
⑤特例(*)の見直しは必要と考えられる。
• 見直し後の必要な単位数については、理容所及び美容所での常勤補助者の就業実態等を把握した上で、履修内容の減免の妥当性等について評価・検討を行うこととしてはどうか。
• 上記を前提に、通知で示されている平成39年度(令和9年度)までの特例の適用期限については、一定の期間延長し、評価・検討プロセス後の特例の見直し方針について養成施設や生徒、理容所及び美容所に十分な周知を図った上で、施行することとしてはどうか。
(*)特例(平成29年改正関連)
通信課程の、面接授業については、120単位以上(600時間以上)の履修が必要とされているが、
・理容所(美容所)に常勤で補助的な作業に従事している者である生徒については、60単位以上(300時間以上)の履修で足りるとする特例を規定。
・面接授業の単位の特例の取扱いについては、平成29年改正後の「理容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準の運用について」等において、 平成39年度(令和9年度)までに一般の生徒と同基準に見直す予定、としている。
事務局案に対する意見を確認した後、芳賀康浩座長(青山学院経営学部教授)は個人的な見解として、現在の実務実習教育がサロン現場に役立っていない根本の原因は試験制度にあるではと指摘した。自動車免許を例にあげ、試験は筆記だけにし実技は養成施設に任せることで、国家試験合格への負担が軽減され、養成施設の裁量で時代にあった実務実習教育が可能なるなどと提言した。
また大森利夫委員(全理連理事長)は、今回の委員会は理美容師教育がテーマとした上で、根本は理美容業そのものにあるとし、理容師美容師のダブルライセンスをさらにバージョンアップし、時代に即した見直しが求められるとし、別途、検討会を設けるべき、と見解を述べた。
【関連記事】
第3回理容師・美容師専門委員会
https://ribiyo-news.jp/?p=44925
タグ: リモート授業, 実務実習, 理容師・美容師専門委員会