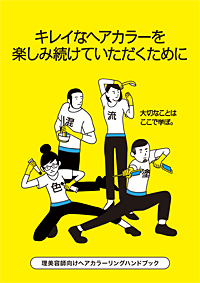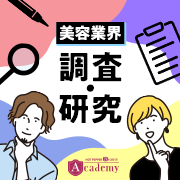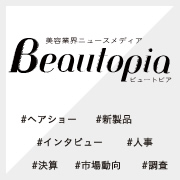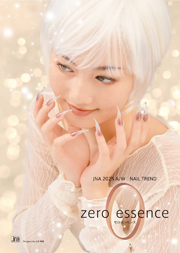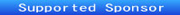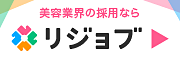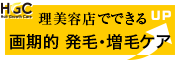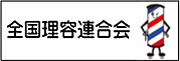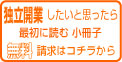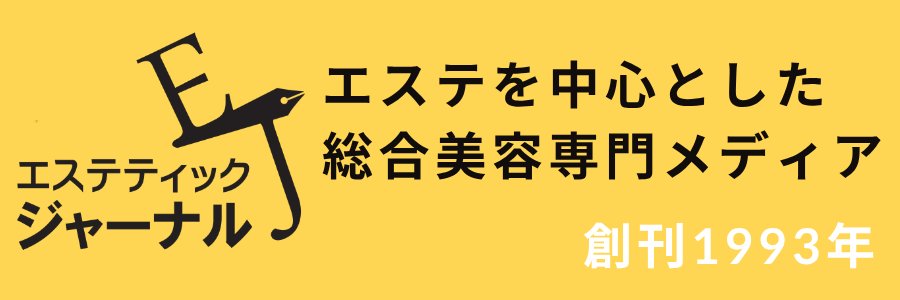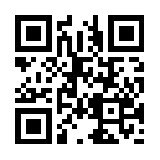日本ヘアカラー工業会が理美容師向けハンドブック
Posted on | 4月 28, 2017 | No Comments
日本ヘアカラー工業会は2017年74月27日記者会見し、ヘアカラーをより安全に使用するための情報提供を行うとともに、理美容業界の協力を求めた。一昨年、消費者安全調査委員会より公表された「毛染めによる皮膚障害」の報告を受けての安全対策の一環で、6月には理美容師向けにヘアカラーリングハンドブックを配布する。

記者会見であいさつする田尾大介日本ヘアカラー工業会(左)と、日本ヘアカラー工業会の対応を説明する、岩瀧正之日本ヘアカラー工業会理美容師啓発専門委員会委員長(会場は、東京・人形町の日本ヘアカラー工業会事務所)
ヘアカラーによる皮膚障害は、毎年約200件前後発生。そのうち理美容店による事故は約7割という。ヘアカラーの消費量はホームユース・プロユースほぼ半々といわれるが、理美容店のプロユースによる事故の発生比率が高い。
しかも一昨年、調査委員会が業界団体に改善を促した後も、事故が減っておらず、同工業会を含め理美容業界団体組織の安全対策への取組みが疑問視れている。
そこで、同工業会では従来の情報・技術・PR・安全の常設4委員会に加え、2016年10月、理美容師の安全啓発を行う「理美容師啓発専門委員会」を新設して、理美容師によるヘアカラー事故の削減を図ることにした。同委員会は、理美容師向け定量調査を行うワーキンググループと、サロン活用ツール・広報ワーキンググループの2つのワーキンググループで構成されている。
理美容師向けのヘアカラーリングハンドブックは「キレイなヘアカラーを楽しみ続けていただくために」がタイトル。A5判、12ページ、発行部数は5万部。編集は、日本ヘアカラー工業会理美容師啓発専門委員会。
6月1日に関係団体に配布するほか、日本ヘアカラー工業会のホームページからダウンロードできる。
【ヘアカラーを楽しみ続けるためのポイント】
日本ヘアカラー工業会(以下当工業会)では、平成27年10月23日に消費者安全調査委員会より「毛染めによる皮膚障害」に関する報告書の公表等を受け、自主基準改正※等を行い消費者や理美容師の皆さまへ情報提供を行ってまいりました。
また同日、厚生労働省生活衛生課より、理美容師の皆さまへの注意事項が発出され、以下の内容が記載されております。
酸化染毛剤やアレルギーの特性や対応策等について確実に知識を身に付けましょう。
酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等についてお客様への情報提供をしましょう。
お客様が過去に毛染めで異常を感じた経験の有無や、施術当日の顧客の肌の健康状態等、酸化染毛剤の使用に適することを確認してください。
以前にかぶれたことのある方には絶対に施術しないで下さい。
酸化染毛剤を用いた施術が適さないお客様に対しては、リスクを丁寧に説明し、酸化染毛剤以外のヘアカラーリング剤を用いた施術等の代替案を提案しましょう。
ヘアカラーの安全性に係る情報等を正確に伝達するため、当工業会では「理美容師向けヘアカラーリングハンドブック」を作成いたしました。
詳細は日本ヘアカラー工業会HPよりご確認いただけます。
(http://www.jhcia.org/)
※平成28年7月12日、当工業会では自主基準を改正し、製品外箱正面の注意表示を新たに記載することに致しました。順次、新表示の製品が配荷されます。
<業務用製品外箱正面の注意表示>
○お客様にヘアカラーのリスクと皮膚アレルギー試験(パッチテスト)の必要性をご説明ください。
○ヘアカラーでかぶれたことのある方には絶対に使用しないでください。
○かぶれを繰り返すと症状が重くなることがあります。
タグ: ヘアカラー, ヘアカラー事故, 日本ヘアカラー工業会