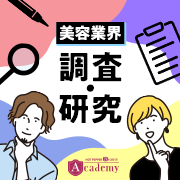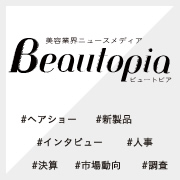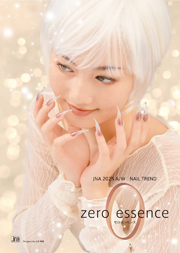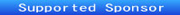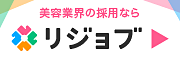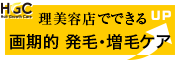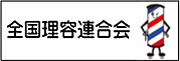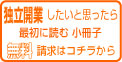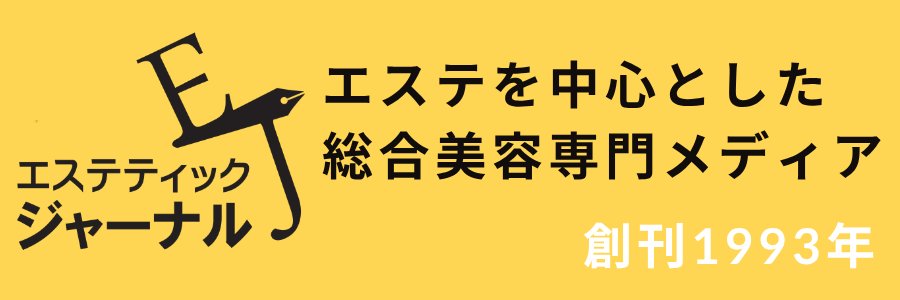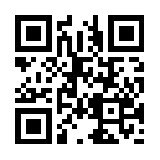全国理容競技大会開催の記念碑を建立へ
Posted on | 10月 12, 2009 | No Comments
 全理連(大森利夫理事長)の第61回全国理容競技大会は、京都府理容組合の実行で京都市で市で10月19日開かれるが、同組有志らは大会開催の記念碑を建立することにし、大会前日の18日、理容業の業祖・藤原采女亮が祀られている京都・嵯峨の御髪神社に奉納する。
全理連(大森利夫理事長)の第61回全国理容競技大会は、京都府理容組合の実行で京都市で市で10月19日開かれるが、同組有志らは大会開催の記念碑を建立することにし、大会前日の18日、理容業の業祖・藤原采女亮が祀られている京都・嵯峨の御髪神社に奉納する。
京都・みやこメッセで開催される第61回全国理容競技大会は、第9回大会以来53年ぶりの京都開催。半世紀ぶりに業祖が祀られた地での開催に、同連は業祖と現在の業界を結ぶご縁ととらえ、「広く国民の美と健康の増進と、理容業のさらなるサービスの向上」を祈念して、記念碑を建立することにしたもの。
除幕式は午後1時30分より、同神社で行われる。

御髪神社(左)と同神社に祀られている髪塚
<理容業の業祖・藤原の采女亮政之(藤原采女亮)>
理容美容の仕事を始めた祖は、藤原の采女亮政之(うねめのすけまさゆき)といわれている。
西暦1200年代のころ、第90代亀山天皇(1259~1274年)の時代に、藤原鎌足の末孫である、北小路左衛尉藤原基春卿という、皇居を警護する武士がいた。彼は、宝物の管理も任されていたが、九王丸という宝刀を紛失したことによってその職を解かれてしまった。
晴基には三人の子供がいたが、協力して紛失した刀を探すことにした。長男は反物商人、次男は染物師となって、京都で宝刀を探した。晴基は三男の采女亮政之を伴って、諸国を歩いた末、下関に移り住んだ。当時下関は、蒙古の襲来で風雲急を告げる九州に渡る交通の要所で、ここを往来する武士の月代を剃り髪結をしながら探索した。また近隣の庄屋の女将の髪も結ったりもした。
この采女亮政之が、髪結の祖、つまり理容美容の祖、とされる。
結局、政之は下関の地に十数年居住し探索を続けたが、晴基は目的を果たすことなく弘安一年(1278)没し、采女亮は3年後(1281年)、鎌倉に移り住んだ、といわれている。
山口県下関市の亀山八幡宮(下関市中之町1-1 )には、「床屋発祥の地」の記念碑がある。
タグ: 御髪神社, 理美容カフェ, 藤原采女亮