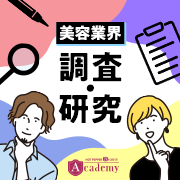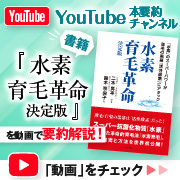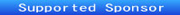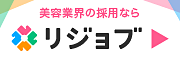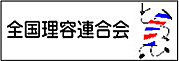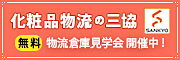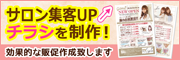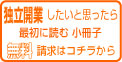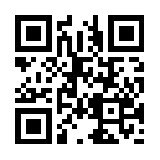日本の理美容の物価指数が低迷しているわけ
Posted on | 9月 29, 2016 | No Comments
 総務省の消費者物価指数によると、日本の理容料金はこの15年間で2.1%上昇した。同じ15年間で、米国は37%、英国は58%も上昇している(*)のと対照的だ。
総務省の消費者物価指数によると、日本の理容料金はこの15年間で2.1%上昇した。同じ15年間で、米国は37%、英国は58%も上昇している(*)のと対照的だ。
理容料金よりはいいが、パーマネントウエーブは5.9%、ヘアカットは5.2%、ヘアカラーは3.9%で、こちらも欧米に比べると、大きく見劣りする。
日本の理美容料金が上昇しない最大の原因は、国民の所得が伸びないからだ。ほかに理美容業界のオーバーショップもある。また、テナント代や光熱水道料などの大幅な値上がりがなく、デフレ状態が続いていることもあげられる。
さらに日本ならではの料金上昇を抑制する要因がある。
欧米でも、日本の1000円カットに似た業態店があるが、日本ほど支持を得ていない。理由は、技術に問題があって、ごく限られた人しか利用しない、という。カット技術の練習を兼ねて業態店で働くケースなどが報告されており、これでは安心して利用できない。
ところが日本の業態店は、カット、あるいはヘアカラーに特化しているだけに、その技術に習熟した技術者が施術している。経済産業省の外郭団体が行った顧客満足度調査で、QBハウスやプラージュが上位にランクインしているのをみれば、これらの店が利用者から評価されているのがわかる。
日本で業態店を利用するのは、限られた人だけではない。普通の人たちの利用も急速に進んでいる。
ブランドサロンを展開する大手サロンも、拡大するこの市場を「メンテナンス市場」と位置づけ、独自色を出した業態店の投入を図っている。
欧米の理美容店は値上げにも積極的で、SNSで店の評価が上がれば値上げするし、技術者がコンテストで入賞すれば指名料がアップするのは当たり前だという。日本では、値上げは客離れの懸念があり、おいそれとはできないのが現状だ。かくして日本の理美容業の低迷は続く。
余談だが、欧米でも耐久消費財をはじめとする物品については、グローバル化もあってデフレ気味だという。欧米の物価を牽引しているのはサービス業とされるが、日本では理美容をはじめとする生活関連サービス、公共サービス、輸送サービスなど総じてふるわず、結果として消費者物価は目標の2%を達成できない。
(*)日本の消費者物価指数に類似した調査。ダイヤモンド・オンライン、2016年9月28日配信記事より引用
タグ: 業態店, 理美容ラウンジ